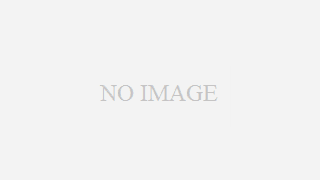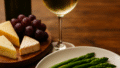こんにちは、あるいはこんばんは!
いつも当ブログを読んでいただきありがとうございます、リクです🍷
今回は「ワインの余韻」について深く掘り下げていきたいと思います。 ワインを飲んだ後、口の中に残るあの余韻――。
「これがあるかないかで、ワインの印象ってだいぶ変わるな」と感じたこと、ありませんか?
実はこの“余韻”、ワインのクオリティを語る上でもとても大切な要素なんです。
🍇 ワインの余韻とは?
ワインを飲んだあとに、口の中に残る香りや味わいのことを「余韻」と呼びます。 それが心地よく長く続けば続くほど、満足感や高級感が生まれます。
余韻を楽しむことは、まるで余白の美学。 主張しすぎず、でもしっかりと心に残る――そんな余韻があるワインは、印象深く感じられるものです。

✅ 余韻を感じる4つのポイント
① 強さ
「強さ」とは、飲み込んだ後に残る香りや味わいの濃さや存在感のこと。 果実味、樽香、タンニンなどがしっかりと残ると、「力強い余韻」を感じられます。
② 長さ
「長さ」は、口に含んでから余韻が消えるまでの時間の長さ。 秒数を数えることで比較もできます。
- 5秒以内:短め
- 6~10秒:中程度
- 10秒以上:長い余韻
高級ワインほど、この余韻が長い傾向があります。
③ 香り
鼻からふわっと抜けていく「香りの余韻」も重要です。 口の中だけでなく、鼻腔を通して感じるアロマが余韻の印象を左右します。
- 飲む前の香りが持続する
- 飲んだ後に新たに立ち上がる香りがある
というパターンもあります。
④ 味わい
飲んだあとに口に残る「味」。 甘味、渋味、苦味などは持続しやすく、 一方で酸味は比較的早く消えるため、爽やかで短めの余韻になることが多いです。
特に味わいと香りがリンクしている場合、余韻の印象がより強く残ります。
🧪 なぜワインによって余韻が違うの?
ワインの余韻の違いには、いくつかの要因があります。
🌞 産地の気候
一般的に、温暖な産地のワインは余韻が長くなりやすいです。 糖度やアルコール度数が高くなる傾向があり、それが余韻の「厚み」に。
🪵 樽熟成
樽で熟成されたワインは、バニラやトーストの香りが口に残ることで、余韻が強く長く感じられます。
🍋 酸味の影響
逆に、酸味が強いワインは、余韻を打ち消す傾向があります。 その結果、後味がすっきりとして短く感じられることが多いです。
🔁 比較してみよう!長い余韻 vs 短い余韻
| 長い余韻の特徴 | 短い余韻の特徴 |
|---|---|
| エキス分やアルコールが多い | 酸味が強く、後味をリセットする |
| 樽香がある(バニラ・ナッツなど) | 粘性が少なく、軽い口当たり |
| 渋味・苦味がしっかりと残る | 味わいが淡く、印象が薄い |
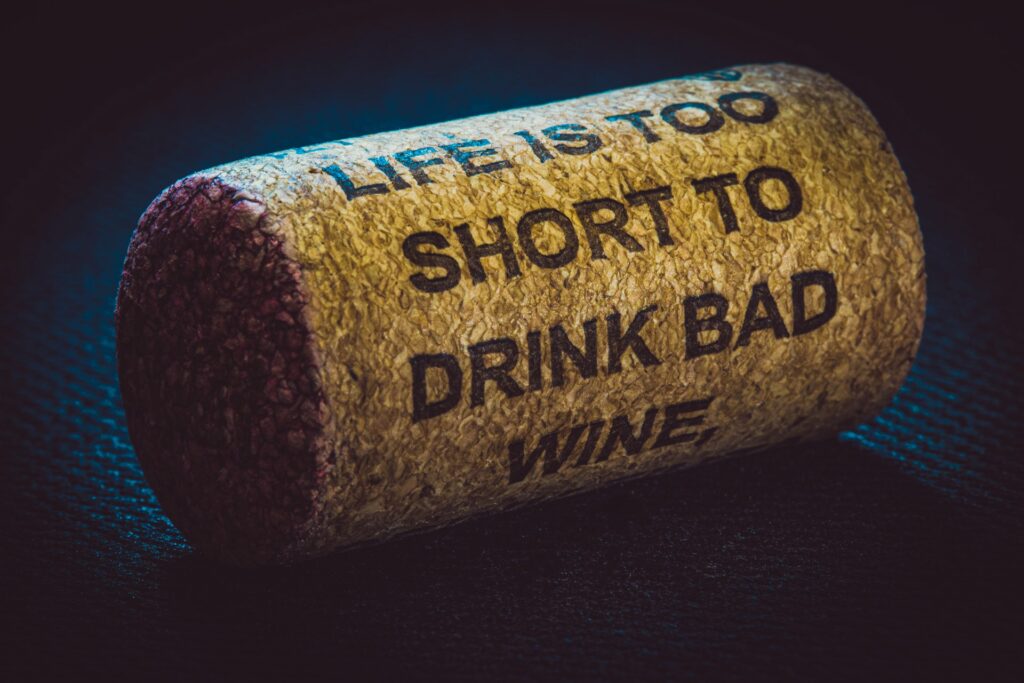
🍽️ 余韻の長いワインに合う料理・合いにくい料理
合う料理(余韻を活かす)
- 赤ワインソース煮込み
- 鴨のロースト
- 熟成チーズ(コンテ、パルミジャーノなど)
- クリーム系リゾット
こうした濃厚な料理は、ワインの余韻を引き立てる「濃厚で風味豊かな」タイプです。
合いにくい料理(余韻を壊す)
- 酸味の強いドレッシングのサラダ
- レモンたっぷりの魚介マリネ
- 生姜やミョウガなど香味野菜たっぷりの和食
これらはワインの余韻をすぐに打ち消してしまう傾向があるので、余韻を楽しみたいときは避けた方が無難です。
💡 余韻を楽しむコツ
- 一口飲んで、飲み込んだ後の5〜10秒を意識してみましょう
- 鼻からゆっくり息を抜くと、香りの変化を感じやすくなります
- ワインを比べるときは、余韻の「長さ」や「強さ」に注目すると発見が増えます
📝 おわりに

「ワインの余韻を感じる」って、ちょっと難しそうに感じるかもしれません。
でも、実は誰にでも感じられるものです。 大切なのは「感じてみよう」と意識することだけ🍷
余韻は、ワインの魅力をじっくり味わうための最後のご褒美のようなもの。 次にワインを飲むときは、ぜひ“余韻”にも注目して楽しんでみてください。
次回は、「料理との合わせ方」についてお話ししていきます。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!
このブログが、あなたの“ちょっと幸せな明日”につながりますように。
では、また!Cheers‼️🥂