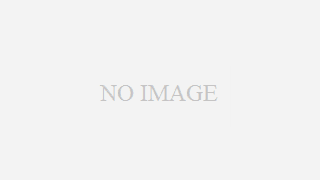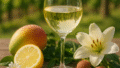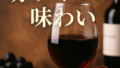こんにちは!あるいはこんばんは!
いつも当ブログを読んでくださって、本当にありがとうございますリクです!
さて、前回は「白ワインの香り」について解説しましたが、今回は、ワインを「口に含んでから」どう味わうのか?その手順を順んで解説していきたいと思います🍷
ワインを「飲む」だけでなく「味わう」ためのステップは意外と細かく、だからこそ面白いんです
ここでは、よく言われる
「1.送り込む → 2.初期印象 → 3.味わう → 4.バランス → 5.余響」
の順で、簡単でも「味わった感想を言葉にしてみよう!」と思えるように、楽しく解説していきます💫

1.送り込む量は、15ml~20ml

香りを楽しんだ後は、いよいよ口に含む瞬間!
ここで「美味しいから」とゴクゴク飲んでしまうのはモッタイな意味での「飲み方」になりがち。
味わうためには、15ml程度をスッと口に含むのがポイント👉
大すぎても少なすぎてもNGです!
2.味わいの初印象を見極めよう👁️
最初の一口は、アルコール感が先に立ちがちです。
その場合は「一度飲んで」「もう一度含む」のが好ましいステップ。
ここで気づけるのが「ワインの一印象」📅
例:
- フレッシュ!で花や果実の香り
- キレがある(清らかな印象)
- 軽やか / まったり / スッキリ / 深みがある…etc
最初は「よくわからない」でもOK
わずかな体験をこつこつ言葉にする習慣を付けていきましょう♪
3.味わいをじっくり確かめる🍋
口の中にワインを含んだら…
「甘味」「酸味」「激味(タンニン)」「苦味」
これらをゆっくり確かめてみましょう📊
少し詳しく解説すると~

- 酸味が立てばスッキリ、キレの良いワイン
- 苦味もバランスがとれていれば香ばしく
- 甘味はあっさり素直でも不思議な魅力を生む
言葉にするのは難しいけど、感じるのは自由です🌿
4.全体のバランスを見ることも大切
上で確認した味わいの要素を、全体の構成として解釈してみましょう!
- 酸味 vs 甘味 のバランス
- 苦味が残りすぎていないか
- 入り口と終わりの結びのよさ
「合わされた味わい」「輝きのある構成」 などの表現もこの段階では有効です🌟

5.余響(あとあじ)にも気を配ってみよう🍃
最後は、飲み込んだ後に口の中に残る香りや味わいを確認します🥛
- すっと消える?
- 香りだけがわずかに残る?
- 甘味がゆっくり続く?
この「余響」の長さも、ワインを表現する不可欠な要素なんです🌼
おわりに~
「飲むだけ」じゃなく「味わう」。
そのためのステップを知ってると、いつものワインがぐっと素敵なものに変わります🌟
最初は、ただ感じたままを言葉にしてみればOK。
言葉を作る。 それはワインを「読む」ことと同じ。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!
このブログが、あなたの“ちょっと幸せな明日”につながりますように。
では、また!Cheers‼️🥂