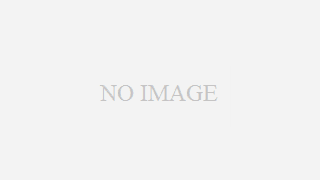― 渋みと酸味が決め手の“深い世界”へようこそ ―
こんにちは、あるいはこんばんは!リクです😊
今回は、赤ワインの味わいについてお話ししていきたいと思います。
第1回目となる今回は、「赤ワインの基本的な味わいの仕組み」からスタートします!
🔍 赤ワインの味わいは、どこからくるの?

赤ワインの味わいは、いくつもの要素が組み合わさって構成されています。
なかでも、赤ワインの“骨格”ともいえる重要なポイントが 渋味(しぶみ)と酸味(さんみ) です。
この2つのバランスが整うことで、赤ワインは奥行きのある、深い味わいを表現することができるんですね。
🧪 渋みと酸味に関わる“発酵のちから”
赤ワインの多くは、「マロラクティック発酵(ニ次発酵)」という工程を経ています。
この発酵によって、ワイン中のりんご酸が乳酸へと変化し、酸味がまろやかにやさしくなるのです。
💡用語解説
- マロラクティック発酵(MLF)
→ シャープな酸味の「りんご酸」を、まろやかな「乳酸」に変える発酵 - 乳酸
→ ヨーグルトやチーズにも含まれる、なめらかな酸味成分。 - 酒石酸(しゅせきさん)
→ ブドウに自然に含まれる、レモンのようなキリッとした酸味の元。
🍇 ブドウの熟し具合と味の変化
ブドウが未熟な場合、ワインには酒石酸が多く含まれ、酸味が強くシャープな味になります。
逆によく熟したブドウを使うと、果実味が豊かで、酸味も穏やかに。
また、渋みの元である「タンニン」は、黒ブドウの果皮や種子から抽出されます。
このタンニンの量や質は、ブドウの品種や醸造方法によって異なります。
🕰 熟成による味わいの変化
熟成された赤ワインでは、タンニンが穏やかに酸化され、丸みのある柔らかい渋みに変わっていきます。
その結果、味に深みが増し、口当たりも滑らかに✨
若いワインの元気な渋みも良いですが、熟成によって変化するワインの表情もまた魅力的ですね。
🧂 赤ワインを構成する味わいの要素
ここで、赤ワインを構成する主な「味の要素」を簡単に紹介していきます👇

✅ 甘味
ほとんどの赤ワインは発酵によって糖分がアルコールに変わるため、甘さはあまり残りません。
でも、ブドウ由来の「果実の甘み」は感じられることもあります。
✅ 酸味
白ワインよりは控えめですが、酸味はワインの印象を大きく左右します。
酸が穏やかなものほど、まろやかで落ち着いた印象になります。
✅ 渋味(タンニン)
これは赤ワインならではの大切な要素。
ブドウの皮や種から抽出されるタンニンの量で、舌や歯茎に残る渋みの強さが決まります。
✅ 苦味
渋みと同じく、タンニンや果皮からくる成分です。
時には「ビターチョコ」のようなほろ苦さとして心地よく感じられることも。
✅ 濃縮感
果実味がギュッと詰まった印象。
「濃い」「しっかりしてる」と感じる赤ワインは、この濃縮感が強い傾向にあります。
✅ ボディ感(厚み)
アルコール度数とタンニンの量が影響。
どっしりとした重厚感があり、「飲みごたえのあるワイン」だと感じる要素です。
✅ 余韻
飲み込んだあと、口の中にどれくらい味が残るかを指します。
コクや渋み、旨味の長さがそのワインの“格”を感じさせてくれます。
📝 まとめ:味わいを知れば、赤ワインはもっと楽しくなる!

赤ワインの味わいは、「甘い・すっぱい・渋い・苦い」といった基本の味が複雑に重なり合ってできています。
これらのバランス、特に渋味と酸味の骨格が、赤ワインの魅力を形づくっているんですね。
同じ品種でも、産地・熟成・作り手によってガラッと印象が変わります。
ぜひこれからは、ワインを飲むときに「どんな味があるか」を意識してみてください!
きっと、1本1本の赤ワインが持つ個性の違いが、もっと感じられるようになりますよ😊
最後まで読んでくださって、ありがとうございました!
このブログが、あなたの“ちょっと幸せな明日”につながりますように。
では、また!Cheers‼️🥂